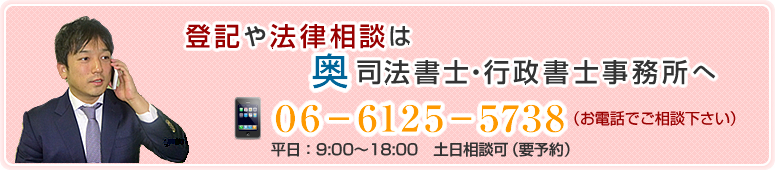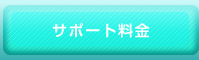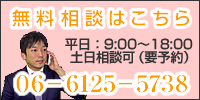
ホームページOPENしました。
役員変更など会社変更登記
役員変更登記とは
役員変更登記とは、会社の取締役や監査役、代表取締役の任期が満了した場合や、辞任した場合、
死亡された場合、解任された場合、また新たに就任された場合等に行う必要な変更登記のことをいいます。
また、退任や辞任によって、定款等に定められた人数を欠くことになる場合は、
役員の退任や辞任の登記はできません。
会社法の規定
閉鎖会社(株式の譲渡制限のある会社)では取締役の員数が1名以上でよくなり、
取締役会の設置も任意となり、取締役の任期も最長10年の範囲で定める事が可能となりました。
監査役の任期も閉鎖会社においては、最長10年の範囲で定める事が可能となりました。
(任期自体は登記事項ではありません)
なお、会社法施行以前からある会社が取締役を3名未満にしたり、監査役を廃止したり、
取締役会を廃止したりする場合には役員変更と別個の登記も必要となる場合があります。
司法書士に依頼されるのに必要な書類
・株主総会議事録(司法書士での作成も可能)
・お客様から司法書士への委任状(会社実印が必要)(司法書士が作成)
その他、場合により
・就任承諾書
・定款
・死亡の記載のある戸籍謄本
・辞任届
・取締役会議事録
・印鑑届出書
等が必要となる場合があります
目的変更
会社の事業目的は定款の絶対的記載事項であり、設立の際には当面の目的と将来予想される会社の事業も含めて
定款に記載したことと思います。
ですが、事業を続けていくなかで、年数が経ちますと諸事情より会社の事業目的の追加等が必要になってくることも多々あります。
そのような場合に、会社の事業目的を変更、追加することを「目的変更」といいます。
なかには事業目的に記載がないと許認可が受けられないような業種もありますので、ご注意下さい。
会社目的の定め方
1.会社の目的とは、会社が営もうとする事業(事業目的)のことです。
定款に記載する会社の目的は、取引社会の通念に照らして、会社の事業内容が何であ るかを知り得る程度に、
具体的に記載しなければならないとされています。
一般的な業種であれば、当事務所の方で、わかりやすく記載することも致します。
2.目的は1つでも構いませんが、多めに記載しておき、柔軟に幅広く事業を行えるようにしておいた方が
良いことが多いようです。
将来行う予定がある事業であれば、当面は行う予定がなくても目的に記載しておくことは構わないので、
何度も登記をするくらいなら、1度にまとめてやってしまうことをお薦めしています。
3.具体的な業種を複数掲げ、その末尾に「前各号に付帯する一切の事業」と掲載すると、
ある程度解釈の範囲が広がります。
4.実務的には、会社の目的の適格事例集を参考にして、会社目的を決めます。
適格事例集に記載されている目的は法務局で認められます。
一方、自分で考え出した単語や言い回しを含む目的は、なかなか認めてもらえないの が実情です。
そのような時こそ、司法書士をうまく活用して、時間の節約をしましょう。
本店移転・支店設置
会社の所在地を変更した時には、本店移転の登記を申請する義務が生じます。
本店移転の登記は、同一管轄内での移転か、管轄外の移転かによって手続の内容がかなり異なります。
同じ管轄内で移転する場合
同一管轄でも同一所在地であれば注意が必要です。
同じ管轄であるかどうか不明な場合は司法書士、あるいは法務局へ相談しましょう。
会社の本店以外に営業拠点を設置する場合
支店設置の登記が必要になります。
本店と異なる場所で単に営業所として設置するような場合には支店設置の登記は必要ありませんが、半永続的に営業の拠点として設置する場合には支店設置の登記が必要になります。
本店移転・支店設置 必要書類
本店移転登記を当事務所へご依頼頂く場合には以下の書類が必要になります。
・全部事項証明書
・役員様の認印・会社印
・当事務所で作成する委任状や株主総会議事録に捺印していただきます。
※この他、ケースによっては別途ご用意頂く場合がございます。
本店移転・支店設置 手続の流れ
1.本店移転・支店設置登記のご相談・ご依頼
2.全部事項証明書の取得
全部事項証明書は、当事務所で集めさせていただくことも可能です。
3.株主(社員)総会議事録・委任状の作成
司法書士が作成しますので、役員で署名捺印していただきます。
4.申請書作成・登記申請
必要書類が全てそろった段階で司法書士が本店移転登記に必要な申請書類を作成し、管轄の法務局に申請をします。
5.登記完了
法務局の混み具合にもよりますが、2~3日後、本店移転登記が完了します。
商号変更
商号のポイント
新会社法施行により、類似商号規制が廃止されました。
ただし、同一所在地で同一商号は用いることはできません。
また、不正競争防止法に抵触する可能性が否定できませんので、穏やかではありますが類似商号の調査は行います。
同一管轄でも同一所在地であれば、注意が必要です。
また、これまでは難しかった商号変更が登記できる機会が増えました。
商号の定め方
商号の中に、「株式会社」、「有限会社」、「合資会社」といった、
会社の形態を表す文字 が含まれていなければなりません。
以前は、ローマ字などを商号登記に用いることはできませんでしたが、現在は日本文字 (漢字、ひらがな、カタカナ)
に加えて、ローマ字、アラビア数字も用いることが可能になりました。
商号変更手続の流れ
1.当事務所に商号変更手続きの相談および依頼をしていただきます。
2.必要書類が揃った段階で当事務所が商号変更登記の申請書を作成し、法務局に商号変更 登記の申請をいたします。
3.当事務所より手続きが完了した旨の書類をお渡しいたします。
増資について
増資は出資する金額を増やしたい場合や、新たな出資者を迎える場合、
または株式会社へ組織変更する際の前提として増資するなど、様々なケースが考えられます。
また、登記簿上の資本金を増額することによって会社の信用性を上げるという効果もありますので、
会社の業績が上がったときなどに利用する事が出来ます。
増資 必要書類
■全部事項証明書(当事務所でも取得可能)
■会社印
■役員の認印
■払込保管証明書(増加した金額が実際にあることの証明書になります。)
増資 手続の流れ
1.ご相談・ご依頼
2.議事録の作成、委任状・株主(社員)総会議事録の作成
司法書士が作成し、ご依頼人で署名捺印していただきます。
3.申請書作成・登記申請
必要書類が全てそろった段階で司法書士が増資の登記に必要な申請書類を作成し、
管轄の法務局に増資の登記を申請します。
4.登記完了
法務局の混み具合にもよりますが、約2~3日後、登記が完了します。
減資について
減資とは、資本金の額を減少することです。
減資の最も効果的な使い方としては、赤字の解消を挙げることができます。
しかし、減資を行うには、まず、株主総会の承認を経なければなりません。
次いで、会社債権者に対して一定の期間(1ヶ月以上)を置いての減資公告、催告をし、
この間に債権者からの意見を求めます(これを債権者保護手続といいます)。
なお、減資を行うには、直前期の決算についての決算公示を行うことも必要となってきます。
減資 必要書類
■株主総会議事録
■一定の欠損の額が存在することを証する書面
■取締役会議事録等
■債権者保護手続関係書類
■委任状
減資 手続の流れ
1.原則として株主総会の特別決議
2.公告・催告
債権者に対して1ヶ月以上の期間をおいて減資公告、催告
3.登記
資本金の減少額などを登記
解散・廃業
会社は事業を拡大させたり、発展していくことが目的ですが、業績が悪化してしまったり、
会社を存続させていくことにメリットが感じられなくなった時に解散・廃業を考える必要があります。
会社には多くの利害関係人がおり、自社のみならず取引先やその他の関係者にも損害を与えてしまう可能性があるため、
早めに手を打つ必要があります。
先行して会社の解散・廃業をすることで、被害を最小限にとどめ、次への展開を前向きに検討していくこともできます。
会社の解散と清算
会社の解散とは、会社運営の業務を終えることをいいます。
会社の解散は、株主総会の決議等で決断されますが、ただ解散をしただけでは完全に会社を閉じたことにはなりません。
この状態では、会社運営の業務を終えているだけにすぎないため、その後、財産の処分、債務整理、
法人税の申告などといった清算業務の手続きがあります。
これら会社解散後の残務整理のことをあわせて清算といいます。
また、この清算業務をする人のことを清算人といいます。
会社の解散から、清算とその完了までの手続きを確認していきましょう。
解散の手続き
1.株主総会での解散決議
2.株主への解散通知
3.解散の届出
4.債権者保護手続き(債権届出の公告など)
5.解散・清算人の登記
6.解散確定申告書の提出
7.清算結了登記
定款変更
定款変更とは、自社の定款に記載されていることを変更することです。その変更した箇所が登記事項の場合は、
法務局への変更登記申請が必要になります。
登記事項とは、以下の様な項目です。
・目的(事業内容)
・商号(会社名)
・本店所在地(本店移転)
・発行可能株式総数
・取締役会、監査役などの廃止
・有限会社の代表取締役変更の登記
・株式の譲渡制限に関する規定
・株券を発行する旨の定め
上記の項目を変更する場合には、法務局に対する登記申請が必要になりますが、
上記以外の項目を変更する場合には、登記は必要ありません。
定款変更の方法
定款を変更する場合には、原則として、株主総会の特別決議によらなければなりません。
場合によっては、もっと厳しい「特殊決議」が必要なケースもあります。
株主総会で定款変更の決議をすると同時に定款変更の効力が生じます。
なお、株式会社の設立時の定款(原始定款)は、公証人の認証を受けなければ効力を生じませんが、
設立後に変更した定款に公証人の認証は不要です。
定款変更を行なう必要がある場合には、当事務所にご相談下さい。